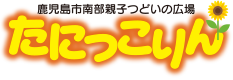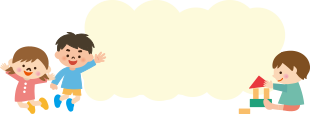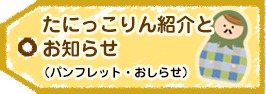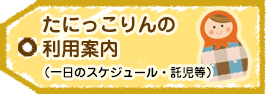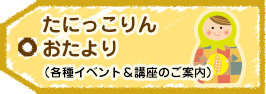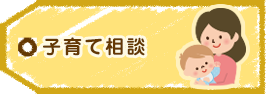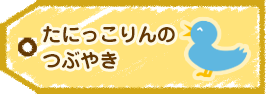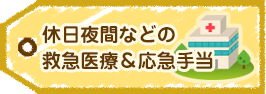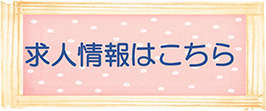子育て相談

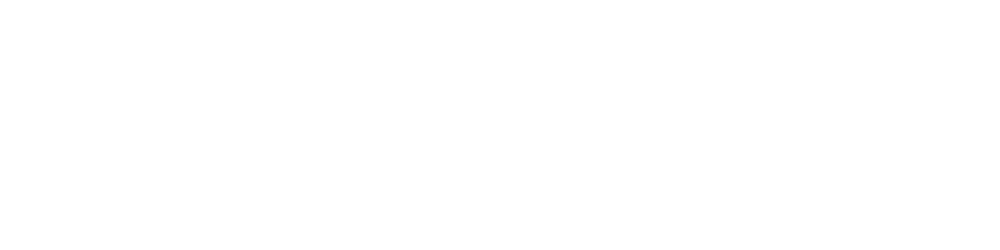
子育て相談
 子どもの窒息と誤嚥
子どもの窒息と誤嚥
新年度になり、新しい環境で過ごす方もいらっしゃるのではないでしょうか。
慌ただしい日々の中でも、少しだけ気をつけて欲しいことがあります。
今回は子どもの窒息と誤嚥についてお伝えします。
子どもの口の大きさは直径約4㎝。トイレットペーパーの芯の直径とほぼ同じ大きさです。窒息が起きる子ども側の要因として、「食べる(嚙む、飲み込む)力」と「食事の時の行動」があります。
窒息につながる背景として、走りまわって食べた、何個もほおばってしまったなどの、食事の時の行動が原因と考えられる事例もあります。
<対策>
◎『食事に集中できる環境作りを』
好奇心旺盛な乳幼児はある程度おなかが満足すると、食事に集中できなくなります。食事の時はテレビを消し、おもちゃを片付けて食卓のまわりをすっきりさせることを習慣づけるとよいでしょう。
◎『水分を摂ってのどを潤してから食べましょう』
◎『一口量を調整しましょう』
丸くつるっとしているものや、固く噛み切りにくいものは食べやすい大きさにカットしましょう。4歳以下の子どもにはブドウやプチトマトは1/4にカットしましょう。
◎『食事に気持ちを向ける工夫を』
「おいしいねー」「これも食べてみようか」などの声かけや、自分で食べられる手づかみメニューをプラスしたり、お気に入りの食器を使ったり、かわいい盛り付けをするなどの演出が、食への興味をアップさせます。
(食育講座より)
 子どもに見えている世界
子どもに見えている世界
大人の目線と子どもの目線の違いを知っていますか?
つい、大人の目線で注意しがちですが、実は子どもには見えていないことも多いのです。
※子どもの視力の発達
・生まれたばかり・・・明るさが分かる程度
・3か月・・・0.01~0.02
・1歳・・・0.2~0.3
・3歳・・・0.8~1.0
・6歳・・・1.0~1.2
3歳頃ではっきり見えるようになり、子どもの目の発達は、6、7歳で完成を迎えます。
※大人と子どもの見え方の違い:視野
大人の視野:左右約150度、上下120度
幼児の視野:左右約90度、上下70度
大人には見える物も子どもには見えていないことがあります。
子どもたちが安全に楽しく過ごせるように、大人が子どものことを知ることもとっても大切です。
 イヤイヤ期も大事な時間です
イヤイヤ期も大事な時間です
子どもたちは日々成長しています。昨日の自分よりも成長している姿は、嬉しいものですが、自我が確立して「イヤイヤ」なると接し方も難しいですよね。
イヤイヤ期は、子どものなかで「自分がしたい」という気持ちにあふれており、自分でして出来なかったり、思うようにいかないとイヤイヤという気持ちになったりして、態度に出てきます。依存から自立していく過渡期です。
困った時は、何かに変換したり、遊びを替えたりしながら過ごすと良いでしょう。
例えば、買い物で走り回る時は、小さなスーパーに行ったり、砂遊びで砂を投げる時は、好きなキャラクターの容器を使って砂を入れて遊んだり、友達が傍に来た時は間に親が入って、投げるという行為から意識をそらすといいでしょう。
おむつ交換を嫌がる子どもには、気に入った物を持たせて遊んでもらっている間に交換するといいかもしれません。子どもが快・不快を感じられるようになり、排泄をすると不快な気持ちになっていると思うので、何かで気を引いて交換するとよいでしょう。
絵本を繰り返し読む子どもに対して、「昨日も同じものを読んだのに・・・」と思うかもしれませんが、子どもは毎日新しい発見があり、同じ本でも違うストーリーだと思っています。心の満足感を得ると同時に、言葉の知識も身についていきます。
こちらの内容は「子育てのヒント講座」に参加されたお母さん達のお悩みも参考にさせてもらいました。皆さんもあてはまることや参考になることがあるかもしれないですね。
 妊婦さんのお正月のお食事
妊婦さんのお正月のお食事
皆さんはお正月どのように過ごされますか?
外出やご家族集まって、ごちそうを食べる機会が多いのではないでしょうか?
お正月は栄養バランスや生活リズムが乱れやすくなる時期です。妊婦さんに気をつけてほしいことをお伝えします。
おせちを含め正月料理はカロリーや糖質が高めで、味の濃いものが多いです。その分、太りやすく、むくみも起きやすいのです。メインの料理は量を控えめにして、野菜たっぷりの副菜などをプラスしたりするのもおすすめです。塩分を控えるために、お雑煮や鍋物、麺類の汁は全部飲まないように意識するといいでしょう。
生ものも妊婦さんには気をつけてほしい食べ物です。
妊娠中は免疫力、消化力が落ちているので、細菌やウイルスに感染しやすくなっています。お寿司やお刺し身等の生魚は避けた方が無難ですが、食べたい時には鮮度のいいものを選んで、食べ過ぎないようにしましょう。まぐろや金目鯛、メカジキは水銀を含むので食べ過ぎに注意しましょう。
生肉や加熱不十分な肉はトキソプラズマに感染して、お腹の赤ちゃんに影響することがあります。レアステーキ、ユッケ、馬刺し、鳥刺し、生ハムなどは控え、加熱をしっかりしたものを食べましょう。
ちょっと意識するだけで、妊娠中も楽しくご家族とお正月料理が食べられます♪
来年のお正月はご家族が増えて、賑やかなお正月になるのではないでしょうか♡
今年もたにっこりんで、スタッフ一同お待ちしています!
 赤ちゃんが生まれてからの生活
赤ちゃんが生まれてからの生活
赤ちゃんが生まれると、赤ちゃん中心の生活になって時間もあっという間に過ぎてしまいます。
今、妊娠中のみなさんは、これから生まれてくる赤ちゃんのことを考えると楽しみでいっぱいですよね♪
喜びと同じくらいたくさんの不安もあると思います。
たにっこりんには先輩ママもたくさん遊びに来てくれます。
お母さんたちの実体験をもとに、初産での大変だったことやご家族の協力で助かったことなどご紹介します。
◎大変だったこと
・まとまった睡眠がとれなくなった
・夜中のミルク作り、洗浄・消毒
・おむつ交換や沐浴(慣れるまでが大変)
・ご飯がゆっくり食べれない
◎お互いに協力し合い、助かったこと
・仕事帰りにご飯を買ってきてくれたり、買い物をして帰って来てくれる
・夜中のオムツ交換・ミルク対応
・わからないことを一緒に調べてくれた
・たくさん写真を撮り合った!
(母親と赤ちゃんのツーショットは自分では撮れません!パパの出番です!!)
妊娠中から産後のイメージをつけておくこともとても大切です。
夫婦で話をする時間を設け、妊娠中から準備できることや、気にかけて欲しいこと、役割分担について話をしておくといいでしょう。
母親1人で抱え込まないことが大切です。赤ちゃんを連れて遊びに行ける場所、お散歩できる場所をピックアップしておくことも大事です。
たにっこりんでは、妊娠中から子育ての時期までご利用できますので、気軽に来られてくださいね。
 ことばを話すために大切なこと
ことばを話すために大切なこと
お子さんのことばがいつ話せるようになるか気になりますよね?
つい、言える「ことば」ばかり気にしていませんか?
◎まずは、ことばを話すために必要な力の準備ができていることが大切です。
・耳は聞こえているかな?いろいろな音に気付くかな?
・言うことがよくわかっているかな?
・人と関わることが好きかな?
・よく声を出すかな?
・まねっこ好きかな?
「よく寝ること」「早寝早起き」「よく遊びよく学べ」を基本に生活することが大切です。
(ことばの講座 言語聴覚士より)
☆たにっこりんでは、言語聴覚士による「ことばの相談」を毎月2回行なっています。予約制の個別相談となっていますので、ご予約を希望される方はお気軽に問い合わせください。
 哺乳瓶の乳首 交換のタイミング
哺乳瓶の乳首 交換のタイミング
最近、赤ちゃんのミルクの飲み方が遅くなったりしていませんか?
たにっこりんに来られたお母さん達の話を聞くと、新生児サイズのまま使っているということを時々お聞きします。
哺乳瓶の乳首にもサイズや種類があります。
最初に哺乳瓶についたままの乳首をそのまま使っていて、交換するのを忘れがちです。
赤ちゃんがミルクを飲むのが遅くなった場合や飲みにくそうにしている時は、交換の時期かもしれません。
★哺乳瓶の乳首サイズの目安★
・SSサイズ新生児 ・Sサイズ1か月 ・Mサイズ3か月 ・Lサイズ6か月
同じ月齢だからといって必ず同じように吸えるわけではなく、個人差を考慮することが重要です。成長の度合いによっては、サイズが大きいものの方がスムーズに吸いやすいこともあります。一生懸命吸わないとミルクが出てこない場合は、途中で疲れて吸うのが嫌になってしまったり、十分な量のミルクを飲めないと、すぐにお腹が空いてしまったりします。
適正年齢にとらわれすぎず「ミルクを飲んだ量」や「スムーズに飲めているか」をチェックして、適切なものを選んであげることが大切です。